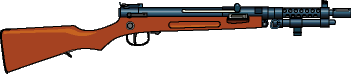名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃 【短機関銃】 †
| 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射形式 | 製造国 |
| 870mm | 3.7kg | 8mm×21 | 30 | F | 日本 |
第二次世界大戦前に日本で開発された短機関銃。アメリカのトンプソンやドイツのMP18などの外国製短機関銃を参考に開発された。
日本における短機関銃の開発は、第一次世界大戦後の1920年代から研究がスタートし、1930年代までには陸軍造兵廠や南部銃製造所によって幾つかの試作銃が作られている。だが昭和6年(1931年)に勃発した満州事変により、従来の火器の生産が優先されたことから、短機関銃の開発は低調となった。
しかし、昭和12年(1937年)に志那事変が勃発すると、落下傘部隊の開発参入や開戦によって増加した軍事費から予算を獲得し得たことで研究は加速され、昭和14年(1939年)には一〇〇式直接の祖となる試製三型機関短銃が完成した。その後の更なる改修試作銃を経て、昭和16年(1941年)、「一〇〇式機関短銃」として完成した。
作動方式は一般的なオープンボルト撃発からのブローバックで、セレクターはなくフルオートのみ。レートリデューサーにより毎分450発程度の発射速度だったが、昭和19年(1944年)より製造された後期型からは廃止され、毎分700〜800発程度となっている。銃身下に着剣装置を備え、制式化前のモデルは二脚も備えていた(前期型以降は廃止)。昭和17年(1942年)から生産された前期型では、一部が改造され、海軍落下傘部隊向けに折り畳み銃床を備えた一〇〇式機関短銃特型も作られている。特型の銃床は二式テラ銃とよく似た設計で、右側面に折畳み、伸張時の固定のため左側に蝶ネジと金具を備えていた。
こうして完成した一〇〇式機関短銃だが、制式化直後の生産はわずかで、昭和17年(1942年)から製造された前期型の生産数はおよそ1000挺ほどにとどまっている。しかし昭和19年(1944年)からは工程の簡素化された後期型が設計され、毎月1000挺ほどが生産された。一〇〇式機関短銃の総生産数はおよそ10000挺だが、うち約9000挺がこの後期型である。
しかし大戦末期のおり、資材不足から充分な弾薬を生産できず、輸送船が撃沈されるなど、兵站が崩壊しかけていたことから前線に数が届かなかった。畢竟、使われる事例も限定的であったが、1945年5月には、本銃を装備した義烈空挺隊(空挺特殊部隊)が沖縄の米軍占領下の飛行場に強行着陸して挺進攻撃をかけ(義号作戦)、航空機を破壊し備蓄燃料を炎上させる損害を与えている。
転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。