
HAS パンツァーファウスト / Panzerfaust 【対戦車擲弾発射器】 †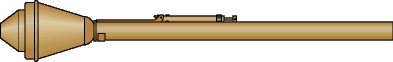
パンツァーシュレックとほぼ同時期に開発された、使い捨て型の対戦車用グレネードランチャー。 戦車猟兵(対戦車戦用歩兵)の装備であったパンツァーシュレックとは異なり、装甲擲弾兵(大戦後期のドイツ軍一般歩兵)の装備として大量配備すべく、極力簡単な構造で作られた。部品は成型炸薬騨である弾頭と、弾頭を射出させる火薬を詰めた発射筒の2つで構成される。 弱点であった射程の短さも徐々に改良が施されていった。1944年の夏に登場した「パンツァーファウスト60」、同年秋の「パンツァーファウスト100」、そして最終生産型の「パンツァーファウスト150」(名前の後の数字がそのまま射程メートル)と次第に射程は延び、連合軍の戦車兵にとって恐怖の対象となった。なお、60型以降では発射方法が変更され、照準器兼安全装置を起こし、発射スイッチを握って押すと発射筒内の火薬に点火し、弾頭を発射する形式になっている。 小型で携帯性に優れた強力な対戦車火器として兵士にも人気があり、終戦までのたった2年間での総生産数は約670万基にものぼる。一方で、配備から間もない頃からドイツ軍がバグラチオン作戦などで大量の装備を喪失していた事もあり、パンツァーファウストも膨大な数がソ連軍に鹵獲されて大々的に使用され、ソ連兵らにも好評であった。
このページの画像はENDOの部屋から転載しています。
転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
|